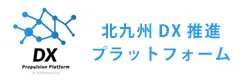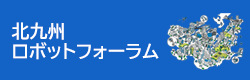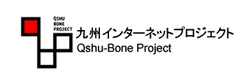【DX LAB KTQ】介護現場の自助具をデジタル化へ─ケア共創ネットワークの3Dプリンタ活用への挑戦
地域DX共創事業「DX LAB KTQ」における共創事例をご紹介します。
今回はケア共創ネットワーク様の事例です。
介護現場の自助具をデジタル化へ─ケア共創ネットワークの3Dプリンタ活用への挑戦
北九州市を拠点に、福祉分野をはじめとした社会課題の解決に取り組む合同会社共創テクノロジーは、これまで培った技術とノウハウを基に、「ケア共創ネットワーク」を設立。3Dプリンタを活用した自助具のデジタル化とノウハウ共有という挑戦的なテーマに取り組んでいます。これにより、利用者の多様なニーズに対応しながら、介護の現場をより楽しく、やりがいのある環境へと変革しようとしています。
今回は、同ネットワーク代表の山﨑駆さんに、その取り組みの詳細を伺いました。

合同会社共創テクノロジー代表 山﨑駆さん
合同会社共創テクノロジーの実績と取り組み
──まずは、共創テクノロジーのこれまでの活動について教えてください。
山﨑さん:当社は工学系の技術をベースに、福祉・介護分野でのDX推進に取り組んできました。特に3Dプリンタ技術を活用した福祉機器の開発が主な事業です。この過程で、介護現場における自助具の製作にも3Dプリンタが活用できるのではないかと考えるようになりました。
──なぜ福祉・介護分野に着目されたのでしょうか?
山﨑さん:率直に言えば、まだ誰も取り組んでいない分野で事業化したいと考えたからです。医療分野と比べると、人と人が接する介護の現場ではDXが非常に進みにくいんです。管理職と現場の意識の差が特に大きく、管理職がDXを進めようとしても、現場が「面倒くさい」と感じると、そこで終わってしまうことが少なくありません。
──これまでどのような課題に取り組んできたのですか?
山﨑さん:介護現場では、複雑化・多様化・高度化するニーズに対応するため、福祉用具の迅速な提供とカスタマイズが必要です。例えば、介護士の方々が利用者のために作る自助具があります。スプーンが握れない方のために握りやすく工夫するなど、現場ではさまざまな工夫をしています。
しかし現状では、紙粘土や100均の材料を使って手作りしており、しかも自腹で材料を買っていることが少なくありません。管理側からすると「そんなに大事なもの?」「食べさせてあげればいいんじゃない?」という認識で、経費計上すらされていないんです。
──課題解決に向けた取り組みについてお聞かせください。
山﨑さん:当社では、3Dプリンタ技術を活用して、この状況を改善できないかと考えました。3Dプリンタを使えば、一度作ったものを再現することが容易になります。また、データとして保存しておけば、必要な時に必要なだけ製作することができます。
特に力を入れてきたのが、現場のニーズに合わせたカスタマイズ機能の開発です。例えば、手の大きさや握力に合わせて自助具の形状を微調整できるようなシステムの開発を進めてきました。
また、技術開発だけでなく、現場での実証実験も重ねてきました。実際に介護施設に3Dプリンタを持ち込み、使い勝手や効果を検証する取り組みも行っています。この過程で、単なる技術提供だけでなく、現場全体のデジタル化支援の必要性を強く感じるようになりました。これにより、現場の負担を軽減し、効率的な業務運営を実現するための次のステップが明確になりました。
──こうした取り組みを進める中で、どのような壁に直面されていますか?
山﨑さん:進めていく上で感じている課題の一つは、3Dプリンタ自体の導入コストです。約6万円で5~6年使えるような3Dプリンタが買えるんですが、そこまでの価値を感じてもらえません。自助具のために、そこまでお金を出してもらえないというのが課題です。
もう一つの課題は機械のメンテナンスです。エンジニアと違って、一般の方は故障の際の対応が難しい。技術だけでなく、継続的なサポート体制の必要性も見えてきました。
ケア共創ネットワークの設立と新たな挑戦
──ケア共創ネットワーク設立の経緯を教えてください。
山﨑さん:これまでの活動を通じて、技術だけでなく、現場のノウハウを共有する仕組みの必要性を強く感じました。そこで、介護業界のノウハウをデジタル化し、共有を促進することで、利用者と現場の双方に利益をもたらす新しい取り組みを始めることにしました。
当社に加え、福祉分野での経営支援を行う株式会社ケアビジネスパートナーズ、介護事業者であるショッピングリハビリカンパニー株式会社とともに、このネットワークを設立しました。さらに、福祉機器開発を行っている大学の研究グループとも連携し、より幅広い視点で課題解決に取り組んでいます。
──具体的な活動内容をお聞かせください。
山﨑さん:私たちは4つの重要な検証を進めています。
1. 介護従事者に教育を行うことで、自助具のデジタル化が可能になるか。
2. デジタル化した自助具を3Dプリントで実際に製作できるか。
3. 教育を受けた介護従事者が他の職員に知識を伝達できるか。
4. 他者が作った自助具のデータを活用できるか。
これらの検証により、現場のデジタル化をさらに進めることを目指しています。
これらの検証のため、段階的なワークショップを開催しています。第一段階では、九州工業大学の学生を講師に招き、3Dモデリングソフトの基礎を学びます。この段階で重要なのは、介護現場の視点を大切にしながら、技術の可能性を理解してもらうことです。
第二段階では、実際に3Dプリンタを使用して自助具を製作します。ここでは、現場のニーズに基づいた具体的な製作実習を行います。特に注目すべき点は、一回目のワークショップで学んだ介護士が、次回では指導する側(メンター)として参加することです。これにより、知識の継承モデルの構築も目指しています。
──人材育成の面ではどのような取り組みをしていますか?
山﨑さん:単なる技術習得だけでなく、デジタル技術を活用して業務プロセスを最適化できる人材、いわゆるDX人材の育成も重要な目標です。ITツールやソフトウェアを使いこなし、現場のニーズに即した新しい福祉用具やサービスをデザインできる人材を育成することで、介護現場全体の効率化と質の向上を目指しています。
ワークショップでは、3Dモデリングの技術習得だけでなく、業務改善の視点や創造性を育むことも意識しています。「この自助具をどうすればより使いやすくなるか」といった課題を参加者同士で議論する時間も設けています。そこから生まれたアイデアを実際に形にすることで、現場発のイノベーションを促進しています。
プラットフォーム構築と地域展開
──オンライン・オンサイトのプラットフォームについて詳しく教えてください。
山﨑さん:まず各地域にリビングラボのような形で、3Dプリンタやモデリング機器を備えたオンサイトプラットフォームを整備します。ここを介護士が自由に利用できる環境として整え、技術習得や情報交換の場として活用していきます。
同時に、デジタル化された自助具のデータやノウハウを共有するオンラインプラットフォームも構築します。このプラットフォームでは、作成した自助具のデータだけでなく、使用時の注意点や改良のアイデアなども共有できるようにします。将来的には、FabLabなどとも連携し、より広範な製作環境の提供を目指しています。
──北九州市で活動する理由を教えてください。
山﨑さん:北九州市は人口が多い政令都市でありながら、少子高齢化率が最も高い都市です。また、アジアに近いという地理的な優位性もあります。近い将来、中国・韓国・インドが日本の高齢化率を追い抜くことになります。そのときに、ここで培ったノウハウや技術を展開できれば、経済的にも大きな可能性が広がると考えています。
まずは北九州市内でモデルケースを作り、その後、周辺地域への展開を図ります。これらの実践を通じて得られたノウハウを基に、全国、そしてアジアへの展開を視野に入れています。
ティール組織による新しい介護の形へ
──「ケア共創ネットワーク」は将来的にどのような組織を目指しているのでしょうか?
山﨑さん:最終的な目標は、ティール組織という新しい組織形態の実現です。これは、全ての現場の人たちが決済権を持ち、上下の指揮系統がないコミュニティのような形態です。ヨーロッパのビュートゾルフという介護団体をモデルにしています。
ビュートゾルフの特徴は、優れたオンラインプラットフォームを持っていることです。様々なノウハウが蓄積され、必要な情報がすぐに取り出せる。私たちも同様のプラットフォームの構築を目指していますが、まずは現場の人たちがノウハウを蓄積できるのか、その検証から始めています。
── 2040年に向けた展望をお聞かせください。
山﨑さん:2040年には高齢化率が35%に達すると予測されています。人類がこれまで経験したことのない超高齢社会です。そこで重要になるのが、省人化できるところは省人化していくという視点です。ただし、単なる効率化ではなく、介護を楽しく、やりがいのある仕事にしていく必要があります。
具体的には、三つの段階を考えています。まず、自助具のデジタル化とノウハウの蓄積。次に、それらを共有できるプラットフォームの構築。そして最終的には、介護現場全体のDX推進とティール組織化です。これらを通じて、持続可能な介護の仕組みを作っていきたいと考えています。
──今後の展開について教えてください。
山﨑さん:いろんなイベントに参加したり、プレスリリースを出していただいたりしているので、それを見てもらって「一緒にやりませんか」みたいに声をかけてもらえるとありがたいです。
3Dプリンターに限らず、「DXに取り組みたいけど何をしたいかわからない」というところからでも構いません。むしろ、こちらからの一方的な提案ではなく、現場の声から始めたいと考えています。「現場がきついのでどうにかしたい」という素直な声から始まり、一緒に解決策を見つけていく。そんなフランクな相談から、新しい介護の形を作っていければと思います。
地域DX共創事業「DX LAB KTQ」について

公益財団法人北九州産業学術推進機構(FAIS)では、令和6年度より地域DX共創事業「DX LAB KTQ」を開始しました。
この取り組みは、北九州地域全体のデジタル化・DX推進のために共創活動に取り組む主体者の発掘から、関係性の構築を目的とした場の提供、共創活動団体の取り組み紹介、課題整理支援や課題解決に向けたソリューション提供企業(IT企業やスタートアップ等)とのマッチング、解決策の共同構築・検証のコーディネートなどを実施します。
この事業を通じ、周囲からの後押しやサポートの輪を広げ、地域内の企業がよりデジタル化・DXに取り組みやすい環境を構築し、北九州地域全体のDXを推進していきます。
これまでの活動については北九州市DX推進プラットフォーム内特設ページをご覧ください。
https://ktq-dx-platform.my.site.com/DXmain/s/meetup/dx-lab-ktq