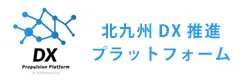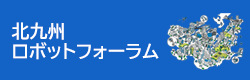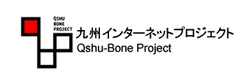【DX LAB KTQ】製造業のデジタル化を共創で推進─北九州IoT実践研究会の多面的な取り組み
地域DX共創事業「DX LAB KTQ」における共創事例をご紹介します。
今回は北九州IoT実践研究会様の事例です。
製造業のデジタル化を共創で推進─北九州IoT実践研究会の多面的な取り組み
「DXは楽しく」---- この意外な言葉が、北九州の製造業を変えつつあります。
2018年に設立された「北九州IoT実践研究会」は、企業間の垣根を越えた情報共有と相互支援を通じて、地域の製造業のデジタル化を推進しています。
現場の課題解決を重視する同研究会の代表を務める、戸畑ターレット工作所DX推進課 課長の中野貴敏さんに、製造業におけるDXの実践と可能性についてお話を伺いました。

株式会社戸畑ターレット工作所 DX推進課 課長 中野 貴敏さん
北九州IoT実践研究会の設立経緯と活動内容
──研究会はどのような経緯で設立されたのでしょうか?
中野さん:発足当時、IoTに関する情報や取り組み方に悩んでいる企業や担当者が非常に多く見受けられました。相談できる相手がおらず、一人で課題と向き合った結果、IoTの取り組みを断念してしまうケースも少なくなかったのです。 そこで、トヨタ自動車九州の「ものづくり研究会」の仕組みを参考に、各企業の課題を共有し、解決策を模索できる場を設けたいと考えました。この構想を具体化するにあたり、公益財団法人北九州産業学術推進機構(FAIS)の協力を得ながら、民間主導で研究会を立ち上げることにしました。
──「課題を共有する」というコンセプトで始まったわけですね。具体的にはどのような活動を展開されているのでしょうか?
中野さん:主に4つの活動を行っています。持ち回り形式の研修会、IoTエキスパートを招いたスキルや便利ツールの勉強会、工場見学、そしてノウハウの共有です。特に工場見学は他社の現場を参考にしたり、具体的なアドバイスを行ったりする場となっています。また、失敗事例とその解決策についても積極的に共有することで、より実践的な知見を深めています。 自分たちで可能な取り組みを模索していこうという方針で、これまで30回近くの活動を重ねてきました。
──研究会ならではの雰囲気作りも大切にされているそうですね。
中野さん:密な仲間作りをしたいと考えていて、年に4回ほど懇親会を実施しています。夏だからビールが飲みたい、年末は忘年会をしたいなどの要望があがります。研究会より、懇親会の参加率が高い方もいます(笑)。
DXへの取り組み
──研究会の代表である中野さんは、もともとDXに関心をお持ちだったのですか?
中野さん:本人はDXをやっているつもりは全然なくて(笑)。当社(戸畑ターレット工作所)は製造業なので、スマートファクトリーの考え方に基づいて、ロボット、IoT、AIを使っていかに生産性を向上するかという事に取り組んでいました。
私はもともと、自動車部品の営業職として、価格交渉に苦心していましたが、根本的な課題解決を目指そうと、生産技術部門に異動し、ロボットとIoTを組み合わせた改善に取り組むようになりました。
──これまでにさまざまなDXの取り組みを行ってきたと思いますが、当初に比べて大きく変化したところはありますか?
中野さん:ディスプレイなどの機材を購入して、社内のデジタルデータを見える化したあたりから、社内の反応が変わってきました。
3~4年前に、カメラを設置して工場内の様子を可視化し、データを取得する取り組みを始めました。それ以前は管理職が現場を巡回して状況を確認していましたが、生産実績データとカメラ映像を組み合わせることで、効率的な現場管理が可能になりました。
──カメラ導入によって現場との関係性に変化はありましたか?
中野さん:はい、非常に良い効果が表れました。これまでは「とにかく生産量を上げろ」といった指示が主流でしたが、IoTを活用して適切な生産量を設定し、品質と作業者の健康を守る管理体制へと切り替えました。 その結果、品質が安定し、労働災害も大幅に減少しました。
特にバリ取り作業では、作業スピードが速い人ほど腱鞘炎を発症するケースが多く、以前は5、6人の離職者が出ていました。 現在はそうした事例が激減しています。作業者の健康を守る方向性が明確になったことで、カメラ導入に対する抵抗もほとんどありませんでした。
データ活用による具体的な効果
──デジタル化による具体的な効果はどのようなものがありますか?
中野さん:原価管理の面では、各工程の所要時間を自動で記録する仕組みを導入しました。その結果、製品ごとの原価を正確に把握できるようになりました。
また、日報のタブレット入力への移行によって、業務効率も向上しました。以前は日報作成を少ない台数のパソコンで行っていたため、定時過ぎの提出となり、お子さんの保育園のお迎えが間に合わないといった声もありましたが、現在では16時55分に作業を終えると同時にデータが送信される仕組みになっています。
──在庫管理の面でも大きな改善があったそうですね。
中野さん:アルミダイカストメーカーとして、在庫管理は常に課題でした。以前は部署ごとにエクセルで管理していたため、全体把握が非常に困難で、実地棚卸で700個もの誤差が生じることもありました。 現在は製造から出荷まで全工程のデータが連携されており、在庫状況をリアルタイムで把握できています。これが収益改善にも大きく寄与しています。
人材育成と働き方の変化
──デジタル化は人材育成の面でも変化をもたらしているそうですね。
中野さん:興味深い現象が起きています。当社は160人規模の企業ですが、年々人手不足が深刻化しており製造現場への新入社員の入社はありませんでしたが、DX推進課には2名入社してくれたという状況です。
現代の若手社員、特にZ世代と呼ばれる世代は、従来型の出世志向とは異なる価値観を持っています。 例えば、DX推進課の若手社員は、「3Dプリンターを購入してくるので、私物ですが職場に設置しても良いでしょうか」と申し出てきました。自分の興味のある事を突き詰めたいということとそれを許容する風土があるかという点も重要なようです。経営陣もこうした主体性を評価し、柔軟に対応しています。自己実現の機会を重視する傾向が、若手の就職先選択の重要な要素になってきているようです。
サイバーセキュリティへの新たな取り組み
──デジタル化が進展する中で、新たな課題も出てきているのではないでしょうか。
中野さん:研究会では昨年度から、サイバーセキュリティに関する新たな取り組みを開始しました。具体的には、JNSA、九州大学サイバーセキュリティセンター、IPA、JPCERT/CC、JASAといった機関やFAISと協働で、「BCP体験型机上演習」の製造業向けシナリオを確立する試みです。 デジタル技術の活用ノウハウは蓄積されてきましたが、セキュリティ面での知見はまだ十分とは言えない状況です。
──具体的にはどのような対策を検討されているのでしょうか?
中野さん:特に重要なのが、インシデント発生時の対応です。中小企業の場合、サイバー攻撃を受けても公表を躊躇するケースが多いのが実情です。 しかし、後になって問題が表面化した際の影響は甚大です。適切な時期の情報開示が、かえって企業価値を守ることにもなります。こうした観点から、セキュリティ対策は経営上の重要課題として取り組んでいます。
研究会の今後の展開と地域貢献に向けた考え
──研究会の今後の活動の方向性をお聞かせください。
中野さん:運営は地域の民間企業が中心となって行っています。会費は徴収せず、有志による運営を基本としています。現在、研究会には17社が参加しており、各社のDXの進捗状況はさまざまです。自立した企業には次のステージに進んでいただき、新たにDXに取り組む企業を支援するというサイクルを確立していきたいと考えています。今後も地域全体の製造業のデジタル化を推進するため、より多くの企業にこの取り組みを広げていきます。
──最後に、これからDXに取り組む企業へのアドバイスをお願いします。
中野さん:印象的な事例があります。ある企業が大型ディスプレイを導入したところ、 現場から「この数値を表示できないか」「工程表を映してはどうか」といった提案が次々と出てくる。デジタル化は、こうした現場の自発的な動きから始めることが重要だと考えています。中には「テレビは映るのか」と言い出す方もいたそうです(笑)。じゃあテレビを見ながらスポーツ観戦とかしたらいいんじゃないかという話も出て。みんな参加できる環境づくりも大事で「これがDXなんだ」と思いますね。DXは楽しくやったほうがいいと思います。
地域DX共創事業「DX LAB KTQ」について

公益財団法人北九州産業学術推進機構(FAIS)では、令和6年度より地域DX共創事業「DX LAB KTQ」を開始しました。
この取り組みは、北九州地域全体のデジタル化・DX推進のために共創活動に取り組む主体者の発掘から、関係性の構築を目的とした場の提供、共創活動団体の取り組み紹介、課題整理支援や課題解決に向けたソリューション提供企業(IT企業やスタートアップ等)とのマッチング、解決策の共同構築・検証のコーディネートなどを実施します。
この事業を通じ、周囲からの後押しやサポートの輪を広げ、地域内の企業がよりデジタル化・DXに取り組みやすい環境を構築し、北九州地域全体のDXを推進していきます。
これまでの活動については北九州市DX推進プラットフォーム内特設ページをご覧ください。
https://ktq-dx-platform.my.site.com/DXmain/s/meetup/dx-lab-ktq