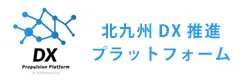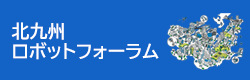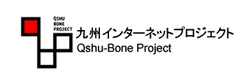【DX LAB KTQ】現場負担を軽減し生産性向上へ─製造業IoT活用研究会の実践
地域DX共創事業「DX LAB KTQ」における共創事例をご紹介します。
今回は製造業IoT活用研究会様の事例です。
現場負担を軽減し生産性向上へ─製造業IoT活用研究会の実践
製造業のデジタル化が急務とされる中、「製造業IoT活用研究会」が北九州で始動しました。この研究会は、地域の中小製造業が抱えるデジタル化の課題を解決するために設立されました。IoT技術を活用して現場の負担を軽減しながら、生産性向上を実現するための支援を行っています。
この記事では、研究会の代表であるイジゲングループ株式会社の平畑輝樹さんへのインタビューを通じて、設立の背景、現在の取り組み、そして地域や業界への影響について詳しくお伝えします。
イジゲングループ株式会社 PDB本部 マネージャー 平畑 輝樹さん
研究会の実績と取り組み
──「製造業IoT活用研究会」設立の背景について教えてください。
平畑さん: 製造業のデジタル化は今後必須である一方で、特に中小企業ではなかなか進まないのが現状です。その大きな理由の一つが、コア業務である製造現場への負荷増加や、プロセス変更による混乱への懸念です。しかし、IoTは使い方次第で現場に負担をかけずに進められます。
バックオフィス業務のデジタル化は進んでいますが、コア業務である中小企業向けの製造現場のデジタル化に効果的なソリューションは、まだまだ少ないのが現状です。今回、研究会として一緒に活動していただく株式会社戸畑ターレット工作所が進められてきたDXの実績を基に、他企業への展開を目指して研究会を立ち上げました。
──なぜ製造業のIoTに着目されたのでしょうか?
平畑さん: 中小企業からよく聞くのが、「現場に負担をかけたくない」という声です。生産活動が止まることは売り上げが止まることを意味し、それは死活問題になります。
一方で現場では、製造現場のプロフェショナルでありながら、ITに精通した人材は多くはなく、IoTが製造業に高い効果をもたらすことが十分に認識されていません。基本的に、新しいことをやるために現場にさらなる負担をかけることは、結構ハードルが高いのです。
IoT導入の課題と解決へのアプローチ
──IoT導入における具体的な課題は何でしょうか?
平畑さん: 最大の課題は「わかりにくさ」です。導入前は「IoTは難しい」「コストが高い」といったイメージを持たれがちです。たとえば、センサー基板の絵を見せた時、ほとんどの人が拒否反応を示すんです。これがやはり導入のハードルの一つになっています。
──その課題はどのように解決できますか?
平畑さん: IoT導入前のイメージと導入後のギャップが埋まらない限り、導入は進まないと考えているんです。そのため、事例を作って見せることが重要です。特に効果的なのが、実際の現場を見てもらったり、知り合いの社長が使っているのを見てもらったりすることです。そういった実例に触れることで、意識は一気に変わります。
──現場での具体的なIoTの活用例を教えてください。
平畑さん: 例えば、1日生産台数をカウンターでカウントしながら、1日100台作りました、それに対して稼働が8時間だったので8で割ると、だいたい1時間あたりの生産台数が分かる、というような大まかな生産計画しか立てられなかったのが実態でした。
IoTを入れることで、生産工程ごとにどれだけの時間がかかっているかを細かく計測できるようになります。例えば、10個生産した後に次の10個分の材料を準備する必要がある場合、材料を運ぶ間に生産ラインが止まるため、ロスが発生してしまいます。このようなロスを可視化することで、効率的な改善につなげることが可能になります。
検証と効果測定
──研究会では、どのような形で実証実験を進めているのでしょうか?
平畑さん:福岡県内で開発されたYokaKitやBravePIといったIoTツールを活用しています。現場での使いやすさを重視して選定していますが、IoTの最大の特徴は、何もしなくてもデータが取れることです。例えば、ヘルメットにセンサーを仕込めば、出勤時にヘルメットをかぶって打刻され、外した時に退勤が記録される。普段する行動の中で、自然とデータが取れるんです。
──検証結果の活用についてお聞かせください。
平畑さん: これが「見える化」の第一歩になります。データを見ることで、どこに課題があるのかが見え、次の手が打ちやすくなります。
IoTを入れたら即何かが起こるわけではなく、まず課題を「見える化」できるというのが良さです。それができないとことには、次の段階でロボットを導入することなどは難しいと思っています。
データ活用と業界マップの構想
──データ活用の展望についてお聞かせください。
平畑さん: レガシーな産業、例えばプラスチックの成形メーカーや板金の加工メーカーは、基本的には機械のサイズは違えど同じような機械を使いながら生産しているんですね。そういう業界ごとに、大きな成果を出している事例を集め、学びながら自社の改善活動を進めることで加速度的に効果を上げることができると考えています。
デジタル化がもたらす競争力
──デジタル化の本質的な価値とは何でしょうか?
平畑さん: 私が考えているのは「デジタル化=単純な業務効率化」だけではないと思っています。得られたデータを活用して何をするか──。特にお客様への価値を向上させるような取り組みが本質的な価値だと考えています。『デジタル化=データ活用』だと思っています。
ただし、 中小企業が中堅企業と同じようにやっていたら、資金力やリソースが違うので、なかなか追いつけないと思っています。一番大切なのは「情報」だと考えています。一番いい情報を早く入手してそれにトライするというのが、とても大切なことです。
そのため、業界マップのような仕組みを作り、我々がしっかりと内容を理解した上で、この業界ではこういうことをやると伸びますよ、ということを提案できればと考えています。
今後の展望と可能性
──研究会の将来のビジョンをお聞かせください。
平畑さん: DXを進めていく上で、まず必要なのが「見える化」です。データがないと分析もできませんし、どこに課題があるか見えません。データドリブンで経営を分析していくことが、今のタイミングでとても大切です。この取り組みにより、現状の課題が明確となり、今後の改善点を洗い出すことができます。
──研究会の組織としての今後の展開は?
平畑さん: この活動を通じて事業化の可能性が見えてきた場合は、ジョイントベンチャーの設立も視野に入れています。私たちイジゲングループ株式会社は、これまでもジョイントベンチャーの設立・運営で実績がありますので、そのノウハウを活かしていきたいと考えています。製造業のIoT導入支援は、一過性の取り組みではなく、継続的なサポートが必要な分野です。組織としても、持続可能な形で活動を続けられる体制を整えていきたいと考えています。
地域DX共創事業「DX LAB KTQ」について

公益財団法人北九州産業学術推進機構(FAIS)では、令和6年度より地域DX共創事業「DX LAB KTQ」を開始しました。
この取り組みは、北九州地域全体のデジタル化・DX推進のために共創活動に取り組む主体者の発掘から、関係性の構築を目的とした場の提供、共創活動団体の取り組み紹介、課題整理支援や課題解決に向けたソリューション提供企業(IT企業やスタートアップ等)とのマッチング、解決策の共同構築・検証のコーディネートなどを実施します。
この事業を通じ、周囲からの後押しやサポートの輪を広げ、地域内の企業がよりデジタル化・DXに取り組みやすい環境を構築し、北九州地域全体のDXを推進していきます。
これまでの活動については北九州市DX推進プラットフォーム内特設ページをご覧ください。
https://ktq-dx-platform.my.site.com/DXmain/s/meetup/dx-lab-ktq