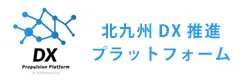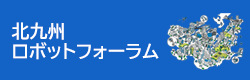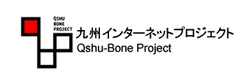【DX LAB KTQ】地域のDX推進を支える学術拠点─早稲田大学IPS・北九州コンソーシアムの取り組み
地域DX共創事業「DX LAB KTQ」における共創事例をご紹介します。
今回は早稲田大学IPS・北九州コンソーシアム様の事例です。
地域のDX推進を支える学術拠点─早稲田大学IPS・北九州コンソーシアムの取り組み
地域産業のDXが求められる中、中小企業の課題解決に向けて2017年に設立された早稲田大学IPS・北九州コンソーシアム。64の企業・団体が参画し、ものづくりと電子情報技術の融合をテーマに、産学連携とグローバル化を推進しています。
同コンソーシアムでは、組織が抱える問題点の顕在化とデジタル技術との相関を考える文化の醸成を目指し、スピード感を持った価値共創のための組織づくりに取り組んでいます。この記事では、早稲田大学理工学術院 教授の吉江修さんに、DXを通じた地域活性化への取り組みと、自治体との連携による新しい可能性について伺いました。

早稲田大学理工学術院 教授 吉江 修さん
コンソーシアムの概要と設立の背景
──まず、北九州市での早稲田大学の取り組みについて教えてください。
吉江さん:2003年に開設した早稲田大学北九州キャンパスは、二つの重要な目的を持っていました。一つはアジアへの近接性を活かしたグローバル化の推進、もう一つはものづくりとICTの融合です。
具体的には、I(インフォメーション)、P(プロダクション)、S(システム)の3要素を柱に、一気通貫の教育研究を目指しました。インフォメーションでアイデアを作り、データ処理し、それをものづくりに生かします。さらに必要に応じてハード化し、システムLSIのような大規模集積回路の実装まで行います。そういった総合的な研究開発拠点として始まったのです。
──その後、コンソーシアムの設立に至った経緯を教えてください。
吉江さん:北九州には、ものづくりの文化が脈々と受け継がれており、環境に配慮した今後の産業を考える上で、多くの生きた教材があります。そこへIndustrie 4.0という言葉に代表される産業の変革の波が押し寄せ、従来から培われてきた日本のものづくり文化も対応を迫られていました。
そこで2017年に、産学連携とグローバル化の視点から、産業の方向性を探るための連携体制として、この「早稲田大学IPS・北九州コンソーシアム」を設立しました。現在では64の企業・団体が参画し、DXを通じた地域産業の活性化に取り組んでいます。
中小企業の現状とDX推進の必要性
──DXへの取り組みを本格化されたきっかけは何だったのでしょうか。
吉江さん:北九州に来て強く感じたのは中小企業の重要性です。早稲田大学本部では大企業向けの取り組みが中心で、ドクター育成や大型研究プロジェクトの実施が多かったのです。しかし、日本の産業の99.7%を占める中小企業が、高い技術力を持ちながらも、従来の産業構造に縛られている現状を目の当たりにしました。
中小企業の経営者の方々は、本当にのっぴきならない状況で頑張っていらっしゃいます。技術力も高く可能性を秘めているのに、今までのやり方で押し込められているような印象を受けました。そこでデジタル技術を活用することで、中小企業の可能性を広げられないかと考え、約8年前からコンソーシアムを通じたDX支援を本格化させました。
DX推進における課題とその克服への道
──DX推進において、どのような課題がありますか。
吉江さん:二つの大きな課題があります。一つは組織内部の課題です。組織がDXを成功させるためには、問題点の顕在化とデジタル技術との相関を考える文化が必要ですが、人的・金銭的リソースの確保が難しいのです。特に人事課が大きな壁になることが多く、トップが「勉強してこい」と言っても、派遣してもらえないのが現状です。
もう一つは中小企業特有の課題です。例えば海外取引では3日以内の見積もり回答を求められますが、従来の長期契約前提の体制では対応が難しいのです。値段も自社では決められず、それは従業員の給与も自由に決められないということを意味します。これまではこの構造が日本の産業の強みでもあったのですが、最上位企業の変化に伴い、むしろ弱みになりつつあります。
──その状況を打開するには?
吉江さん:デジタル技術を積極的に導入しようとする担当者がリーダシップをとることができる雰囲気づくりが大切だと思いますが、えてしてこの役割に就く人は社内で孤立してしまうという問題があります。これはかつてのインターネット導入期と同様の状況です。当時も新しい技術に取り組む人は「変人扱い」されましたが、4~5年経つと評価が変わっていきました。社内の課題解決に、これから実施されるDX推進活動がどのように結びつくのかを明確にすることが大切だと思います。
コンソーシアムの活動内容と目標
 早稲田大学北九州キャンパス(若松区ひびきの北九州学術研究都市に立地)
早稲田大学北九州キャンパス(若松区ひびきの北九州学術研究都市に立地)
──本DX共創活動におけるコンソーシアムの具体的な内容を教えてください。
吉江さん:今年度は「官民一体となった強い組織づくりとDX推進」をテーマに、二つの重要なワークショップを開催しています。一つ目は、元PTCジャパン株式会社の後藤智氏をファシリテータとして招き、組織が抱える問題点の顕在化とDX戦略策定について実践的な討議を行います。
二つ目は、パーソル総合研究所の本間浩輔氏を招いて1on1をテーマに、人材育成と組織強化について学びます。DX部会、人材育成部会を中心に、DXの導入・推進方法、DX人材の育成、共創の思想のもといかにして強く持続可能な組織体質を培っていくかについて議論を重ねてきました。
──具体的にはどのように進めているのでしょうか。
吉江さん:段階的なアプローチを取っています。まず、コンソーシアム内で議論を続けてきた内容を共有し、方法論としての実践段階に移行します。コンソーシアムの構成員と北九州市職員を対象に参加を募り、官民一体となったDX推進のレベルを上げることを目指しています。
この成果をコンソーシアム構成員で共有し、事例を収集し、方法論の一般化に結び付けています。
地域の特性を活かした取り組みとその広がり
──北九州で活動する意義についてお聞かせください。
吉江さん:北九州は人口が多い政令指定都市でありながら、少子高齢化率が最も高い都市です。また、アジアに近いという地理的優位性があります。近い将来、中国・韓国・インドが日本の高齢化率を追い抜くことになりますが、そのときに、ここで培ったノウハウや技術を展開できる可能性があります。
──北九州市の特徴的な面はどのようなところでしょうか。
吉江さん:日本の歴史を見ても、大きな変化は西から起きていることが多いのです。北九州キャンパスと早稲田本部の関係も同様で、あまり強い制約を受けないため、海外の大学との提携や同時学位取得など、革新的な取り組みが可能になっています。早稲田大学として協定を結んでいる大学とは別に、独自に協定を結ぶことにより積極的にグローバル戦略を打ち出せる自由さがあります。このように、北九州市では「何か新しいこと」に取り組みやすい雰囲気があります。
持続可能なDX推進と地域連携の未来
──今後の展開についてお聞かせください。
吉江さん:まず基盤づくりとして、早稲田大学内の「研究交流事業」の仕組みを利用し、寄付・共同研究による運営基金を確保することで、持続可能な活動基盤を築いていきます。また、これまで2年間実施してきたリカレント教育プログラムのカリキュラムに、コンソーシアムでの成果を組み込み、広くDXの普及を行っていきたいと考えています。
──より具体的な展開の予定はありますか。
吉江さん:現在のコンソーシアムでの関係をさらに発展させ、本当の意味でビジネスの上で付き合えるような段階に進むことを目指しています。例えば、早稲田大学が会社を作って、AIのこれこれの技術といったら、この会社に頼めば何とかなるといった、一つの核になるような、実際にビジネスで付き合えるようなものがコンソーシアムの中に生まれるといいですね。
企業規模や業態に関係なく、対等な立場で意見交換ができる環境を整え、大企業と中小企業が相互に学び合える場を創出していきます。
──地域全体としての展望はいかがでしょうか。
吉江さん:北部九州全体でのネットワーク形成も重要だと考えています。昨日も古賀市で、あるグループとお話をさせてもらいましたが、北部九州各地でいろんな活動が起きています。コンソーシアムに入ってくださいというのではなく、それぞれの地域の活動とネットワークでつながることを目指していきたいと考えています。そうした連携を通じて、この地域全体でDXを推進していければと考えています。
DX成功のために必要な要素とアプローチ
──最後に、DXを成功させるための要点をお聞かせください。
吉江さん:三つの要素が重要です。まず技術知識の習得です。それから、みんなで作り出すような、どのくらいの人が協力してくれるかとか、引っ張っていく人がいるのかとか、問題設定が適切にできるかとか、そういう共創、共に創る力をつけてもらいます。そして、やみくもにやっても危ないので、世の中のレベルや自分の立ち位置を把握し、適切な方向性を見定める俯瞰する力です。
この状況を変えていくために、コンソーシアムとしてできることを一つずつ実践していきたいと考えています。
地域DX共創事業「DX LAB KTQ」について

公益財団法人北九州産業学術推進機構(FAIS)では、令和6年度より地域DX共創事業「DX LAB KTQ」を開始しました。
この取り組みは、北九州地域全体のデジタル化・DX推進のために共創活動に取り組む主体者の発掘から、関係性の構築を目的とした場の提供、共創活動団体の取り組み紹介、課題整理支援や課題解決に向けたソリューション提供企業(IT企業やスタートアップ等)とのマッチング、解決策の共同構築・検証のコーディネートなどを実施します。
この事業を通じ、周囲からの後押しやサポートの輪を広げ、地域内の企業がよりデジタル化・DXに取り組みやすい環境を構築し、北九州地域全体のDXを推進していきます。
これまでの活動については北九州市DX推進プラットフォーム内特設ページをご覧ください。
https://ktq-dx-platform.my.site.com/DXmain/s/meetup/dx-lab-ktq